この画像はアニメ「ジョーカーゲーム」の第9話
ダブルジョーカー後編の1シーンです。

このシーンを見た瞬間に、思わず「アッ」と叫んでしまいました。

家を第三者の立場でサポート
一昨日の7月1日に相続路線価が発表されました。
相続路線価は相続税を計算するための数値で、
その年の1月1日時点での土地の価格が基準となっています。
相続路線価について詳しくはこちら
⇒路線価(相続税路線価)とは
近畿地方ではここ5年間連続して、相続路線価が上昇しています。
次の図は京都の四条烏丸付近で、2017年と2020年の同じ場所の相続路線価を比較したものです。
先日、お引き渡ししたお宅ですが、
こんな状態でした。
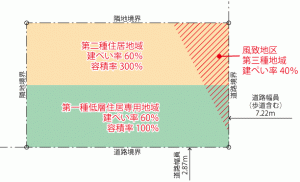
敷地の北半分が第二種住居地域、
南半分が第一種低層住居専用地域、
更に一部が風致地区になっていました。
そしてこちらが、完成した家です。
「住宅の建築工事の流れ|着工から完成までの工程」
というページを作成しました。

アップしたページでは、時系列に並べて単純に表現していますが、実際の住宅の工事には無数の工程があり、錯綜して複雑に絡み合っています。
かつて、私は何度も大失敗をした事があります。
「上棟式の秘話-おかめの哀しいヒストリー」という動画を制作しました。
こちらです。
(動画長さ 4分15秒)
「おかめ」という名前は知っていても、具体的に誰なのかはよく分かりませんよね。
実は「おかめ」にまつわる哀しいお話があるので、取材してきました。
今日のニュースで路線価が発表され、私の住んでいる京都では東山区の四条通りが43.5%の上昇率で全国2位の上昇率だったとか。
ところで路線価って何?
路線価は毎年、7月ごろに発表されるのですが、各道路毎に、その道路に接している土地の、半年前の1月1日時点での評価額を表します。
相続税や贈与税を計算するのに必要な数値になります。
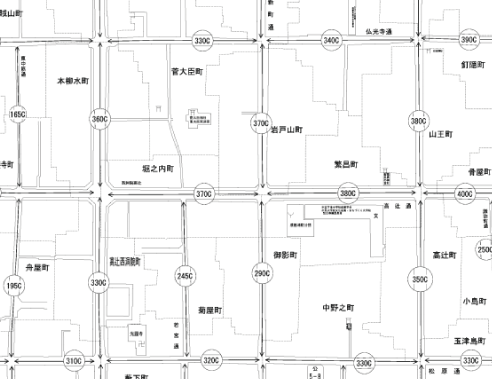
路線価は上のような形で地図上に表記されます。
先日、上棟した現場の動画をアップしました。
「上棟の瞬間、その時‥|御幣の気になる話」
上棟の瞬間、他に気を取られていて、見逃してしまいました。
気が付くと、既に棟木が上がっていたのでした。
京都市上京区の現場が上棟しました。

特にあらたまって上棟式を行う事はしませんが、
お施主さんの方でお酒を用意し、大工さんたちに持って帰ってもらようにされていました。
また、小屋裏に納める御幣も用意してありました。
関西で上棟の御幣と言えば、おかめ御幣ですね。
HPに『床の間の様式と種類|真・行・草』という記事をアップしました。
こちらです↓
『床の間の様式と種類|真・行・草』
最近の新築住宅では、和室を設ける方はいらっしゃいますが、床の間を設ける人は少数です。
床の間と接する機会があるとしたら、旅行先で宿泊する旅館ぐらいなものでしょうか。
普段、あまり接する機会が無いと、床の間にどう対応してよいのか分かりませんよね。

例えば上の写真の様な場合、誰がどこに座るのか決まりがあるんですよ・・・。
「ローコスト住宅の実態」の動画をYouTubeにアップしました。
実際にローコスト住宅のハウスメーカーで家を建てた方を取材してきましたので、どの様な状況なのか、ご覧になってください。
この様な状況になってしまったのには、動画では出てきませんが、色々と事情があるのでした。

京都市北区で工事が始まり、現在、基礎工事が完了したところです。
コンクリートを流す前に、私の方で鉄筋の配筋状況をチェックしました。
当然ですが、基礎が完成してしまうと、中の鉄筋がどのような状態なのか分からなくなってしまいます。
<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- モバイル用バナー -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:320px;height:100px"
data-full-width-responsive="true"
data-ad-client="ca-pub-0462090798236012"
data-ad-slot="1019589246"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
10年前に私のサポートを受けて注文住宅を建築されたお客さんのお宅を訪問してきました。
築10年とは思えないほど、とても綺麗に住まわれていました。
ただ、今だからこそわかる、失敗したなと思う点、成功したなと思う点。
新築してからこの間、家族の変化やライフスタイルの変化などがありましたので、設計の段階では予期していなかった事も多々あります。
実際に体験した人だからわかる、注文住宅の失敗と成功の事例をインタビューしてきましたので、ご紹介します。
ラスモルタルというのは
ラス網と呼ばれる金属製の網を下地にして、モルタルを塗って仕上げる工法のことです。

1980年代ぐらいまでは、木造住宅の外壁と言えば、このラスモルタルが最も一般的な仕上げでした。
ところが、今では新築の現場で、ラスモルタルをほとんど見なくなりました。
なぜなのでしょうか?
これまで、工務店と詳細を詰めていたIさんが
請負契約を交わす事となりました。

競争入札の時点では
地下室を設ける事になっていてグランドピアノを置く予定になっていました。
しかし、地下室は断念する事になりました。
地下室には色々なメリットとデメリットがあります。
住友林業で家を建てたという方から
電話でご相談がありました。
話を聞くと、沢山の不具合がり不信感が募ったものの
とりあえず、細かな不具合は一通り直してもらったようです。
ところが、奥の敷地境界が
図のような状況になっていて、どうしようもない状況のようです。
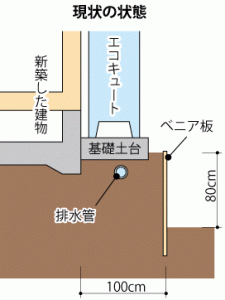
コンパネ(べニア板)で土留めをしているだけなので、
このままの状態では、土留めが崩壊して、
家が傾きかねないです。
なぜ、この様な状態になってしまったのか?
詳しくはこちら→このままだと家が傾いてしまいます
相談者の方は現在、住友林業と交渉をしているのですが、
難航しているようです。
「AMP」(アンプ)というのをご存知でしょうか?
スマホやブレットでホームページにアクセスした際に
高速で表示させる手法のことです。
例えば、スマホやタブレットで
「ハウスメーカー 比較 一覧表」と検索してみてください。
広告の下にある
ハウスメーカーを比較する一覧表【評判・坪単価・特徴】
というのが当社のサイトです。
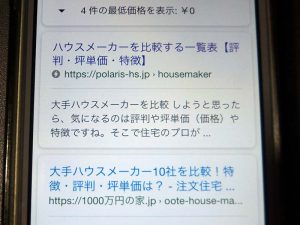
いかがです?
他に表示されているサイトとちょっと違うところがあるんですが
お分かりになるでしょか?
現在、詳細打合せを進めているIさんが
パナソニックのショールームにて
キッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレ
の仕様を確認。

その時の様子を動画に撮影させてもらいました。
実は住宅設備のショールームを見学する際には
チョッとしたポイントがあります。
妻が足を骨折してしまいました。
全治3か月の診断。
朝起きて、半分寝ぼけた状態で階段を下りて
最後の一段を踏み外したのでした。

それ以来、大ピンチに陥りました。
掃除に洗濯に食事・・・。
一体どうしたら良いの?
我が家は完全に機能停止状態になってしまったのです。