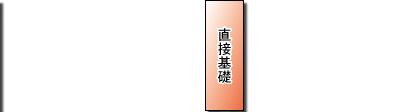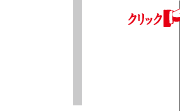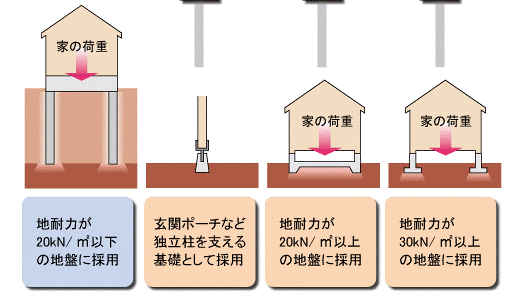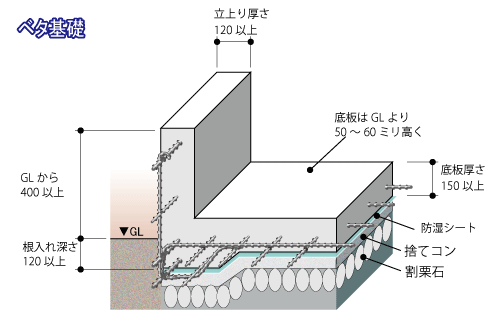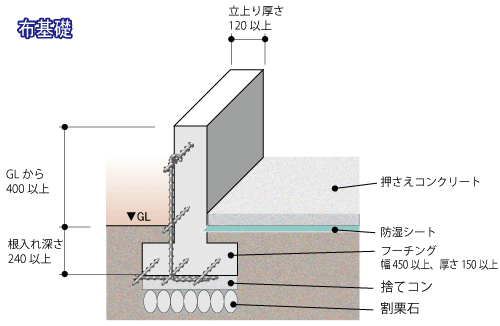業務内容
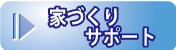
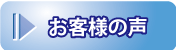
住宅業界の情報
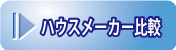
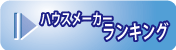
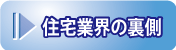
家づくりの知識
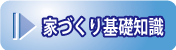
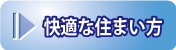

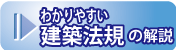
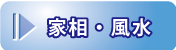
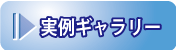
その他の基礎知識
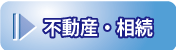
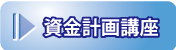
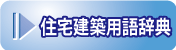
サイトの管理人

(株)ポラリス・ハウジングサービス
代表取締役 高田公雄

YouTubeチャンネル
家づくりのノウハウがいっぱい
毎週金曜日に動画配信しています。

基礎は住宅の足元を支える大切な箇所です。
住宅の基礎工事にはいくつかの種類があり、敷地の地耐力に応じて適した基礎工事を選択することが重要です。
しかし、施主にしてみたら、我が家の基礎工事が しっかり行われているのかどうか、なかなか判断できません。
このページでは住宅における基礎工事の種類と最低限押さえておくべき注意点を分かりやすくご紹介します。
住宅の基礎工事の種類
ベタ基礎と布基礎がメイン
木造住宅の基礎は、直接基礎と杭基礎に大別されます。
直接基礎にはベタ基礎、布基礎の2種類の基礎工事があり、これ以外に独立柱を支える独立基礎があります。
なお、異なる構造の基礎を併用することは建築基準法で禁じられていて、
もし、併用する場合は構造計算により、構造耐力上の安全性を確認する必要があります。
ベタ基礎と布基礎の違い
基礎工事の注意点
動画で実例を解説
基礎工事の様子を動画でご覧ください。
チェックポイントなどを分かりやすく解説しています。
住宅業界の関係者からも分かりやすいと好評をいただいている動画です。
動画長さ3分40秒
チェックポイントを図解で解説
出隅部の補強
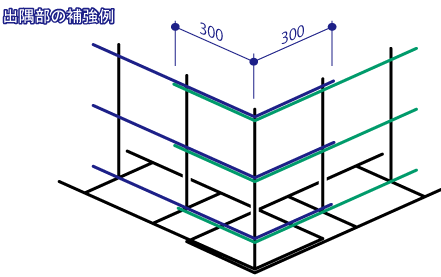
隅部の横筋は折り曲げて、それぞれ300mm重ね合わせる。
鉄筋の継手の長さ(重ね代)
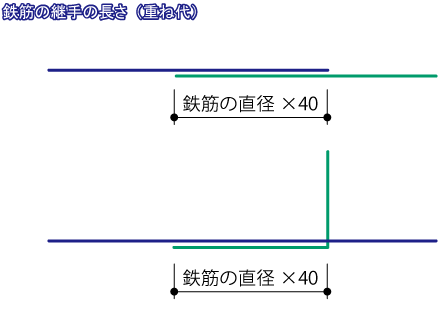
鉄筋が短く、途中でつなげる場合、あるいはT字やL字の箇所で鉄筋をつなぐ場合、鉄筋の重ね代の長さは、鉄筋の直径の40倍以上必要とされています。
直径10ミリの鉄筋(D10)であれば、400ミリ。
直径13ミリの鉄筋(D13)であれば、520ミリ。
換気口の補強
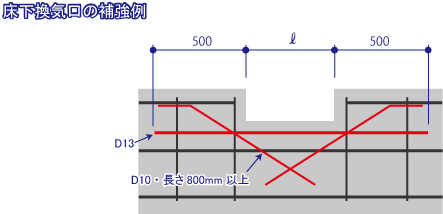
基礎に換気口を設ける場合、換気口の周りはD13横筋およびD10の斜め筋により補強する。
D13横筋の長さは換気口の幅+両側500mmとする。
D10の斜め筋の長さは800mm以上とする。
※Dは鉄筋の直径のこと
貫通口の補強
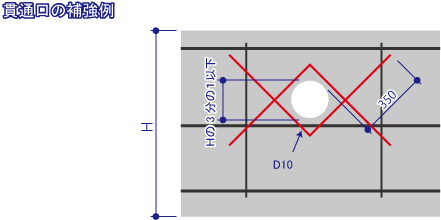
設備の配管や電気の配線のために貫通口を設ける場合、
D10の鉄筋により、図のように貫通口の径より350mm飛び出させて補強する。
また、貫通口の径は立上り高さ(H)の3分の1以下とする。
※Dは鉄筋の直径のこと
人通口の補強
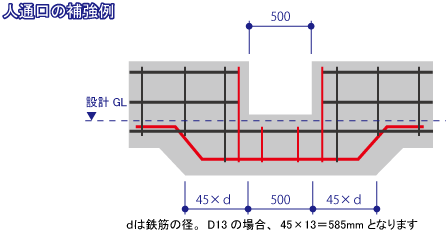
人通口を設けると、立ち上がりに欠損が生じるため、補強が必要となる。
図はその一例。地中梁せいは補強範囲を許容力度計算で求める。
ベタ基礎の底板部のかぶり厚さ
ベタ基礎の場合、基礎底部の土と接するコンクリートのかぶり厚は6cm以上確保しなくてはなりません。
キューブ状のスペーサーを使って、鉄筋を地面から6cm以上浮かせます。
その際、スペーサーには長辺と短辺があるので、長辺を使って浮かせないと、6cm以上が確保できないので注意が必要です。
立上り部のかぶり厚さ
基礎の立上り部のかぶり厚は4cm以上を確保しなくてはなりません。
型枠の中で、鉄筋が偏っていると4cmのかぶり厚を確保できない場合があるので注意が必要です。
立上り鉄筋のコンクリートの付着
鉄筋コンクリート構造はコンクリートと鉄筋が一体となることで耐力を発揮します。
底板のコンクリートを打設する際にコンクリートが付着してしまうことがあります。
この付着したコンクリートは耐力を期待できませんので、このまま立上りのコンクリートを打設してしまうと、所定の耐力が得られない可能性があります。
コンクリートのジャンカー

コンクリートを流し型枠を外すと、コンクリートが隅まで回らず凹んだ状態のまま固まっている事があります。これをジャンカーと呼びます。
ジャンカーは表面部分だけが凹んでいるのであれば問題ありませんが、奥深くまでこのような状態になっていると、期待する強度が得られません。
写真のようなジャンカーも、上から化粧モルタルを塗ってしまえば分からなくなってしまうので、注意が必要です。
★オススメの記事