業務内容
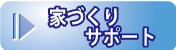
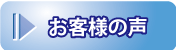
住宅業界の情報
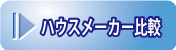
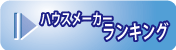
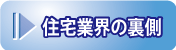
家づくりの知識
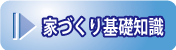
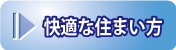

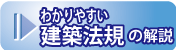
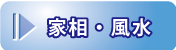
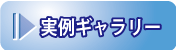
その他の基礎知識
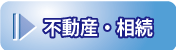
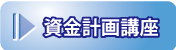
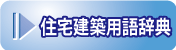
サイトの管理人

(株)ポラリス・ハウジングサービス
代表取締役 高田公雄

YouTubeチャンネル
家づくりのノウハウがいっぱい
毎週金曜日に動画配信しています。

土地や建物などの不動産を売買する際に、「不動産登記」が必ず発生します。
しかし、普段の生活で不動産登記に関わる事は稀なので、何をするのか? なぜ必要なのか? しっかり理解できている人はあまり多くありません。
ここでは不動産登記について、わかりやすく簡単に解説します。
登記の関連記事
![]() 登記事項証明書とは?
登記事項証明書とは?
‥‥登記記録とはどんなものか?
![]() 登記記録の表題部
登記記録の表題部
‥‥表題部には何が記載されているのか?
![]() 登記記録の権利部
登記記録の権利部
‥‥権利部には何が記載されているのか?
![]() 登記申請の手続き
登記申請の手続き
‥‥売主と買主が共同で登記申請をする
![]() 仮登記とは
仮登記とは
‥‥先にツバを付けておくというのが仮登記
![]() 登記とは【住宅建築用語】
登記とは【住宅建築用語】
‥‥登記の仕組みを解説
不動産登記とは何?
公的な帳簿に記載すること
不動産登記とは、不動産の所有者など、権利関係の情報を公的な帳簿(登記簿)に記載することです。
登記した内容は一般に公開されていて、所有者以外の人も閲覧できます。
不動産登記によって、その不動産の権利関係などの状況がどうなっているのかを明らかにできるので、第三者に対し主張する事が可能になります。
不動産登記に記載する内容
不動産登記に記載する内容は概ね次の通りです。
- どこのどの様な不動産なのか?
場所や大きさ、建物であればどんな構造なのかなど - 誰が所有しているのか?
所有者の氏名や住所、不動産の変遷した履歴など - 抵当権などがどうなっているのか?
どの金融機関からその不動産を担保にした借り入れがいくらあるのかなど
これらの情報は法務局や登記所、またはネットで誰でも閲覧でき、登記内容を記載した登記事項証明書(登記簿謄本)を入手する事もできます。
登記事項証明書について詳しくはこちら
登記記録はプライバシーな情報ではない
登記記録は権利関係を公示するものなので、戸籍謄本や住民票とは違い、プライバシーな情報ではありません。
見ず知らずの赤の他人でも、登記事項証明書を交付してもらえます。
なぜプライバシーな情報ではないのか?
次の様な例を考えてみてください。
近所に空き家があり、老朽化が進んで、今にも崩れそうな状態になっていたとします。危険なので空き家の所有者に何とかしてもらわなければなりません。
しかし、長年の間、空き家になっていたので、代も入れ替わり、近所の人達はその家の所有者の事を誰も知りません。
そこで、法務局に行って登記事項証明書を交付してもらえば、だれが所有者なのかが明らかになり、所有者と連絡を取る事ができる様になります。
これがもし住民票の様に、不動産の所有者本人しか交付してもらえないとしたら、近所の人達は空き家の所有者を調べる事ができず、危険な状態のまま放置するしかありません。
※実際はこの様なケースの場合、所有者は既に亡くなっていて、移転登記もされておらず、現在の所有者が誰なのか分からない事が多々あります。
登記事項証明書は法務局や登記所で交付してもらうのですが、不動産を登記している最寄りの法務局だけではなく、全国の法務局が、オンラインで結ばれているので、プリントアウトして交付してもらえますし、ネットで申請して取得する事もできます。
なぜ不動産登記をするのか?
不動産登記をする事にどんな意味があるのでしょうか?
不動産登記法によると
不動産登記法の第1条には次のように記載されています。
不動産登記法 第1条
この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
※衆議院HP「不動産登記法」より
「登記によって国民の権利の保全を図る」という事ですが、どういう事なのでしょうか?
次のような例を見てみましょう。
もし、登記してなかったら
例えば二重売買があったとしたら、どうどうなるでしょうか?
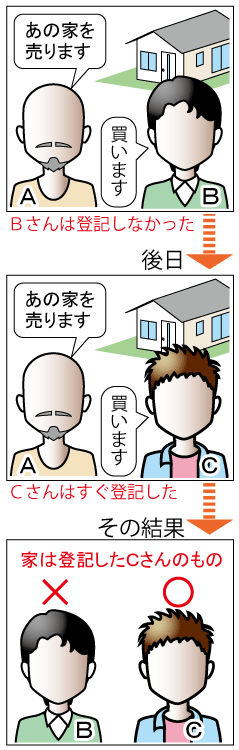
Aさんが所有する不動産をBさんとCさんの両方に売ったとします。
Aさんが悪意を持って二重売買をした場合、どちらに所有権が移るのかわからなくなってしまいます。
しかし、Cさんが先に移転登記をしていれば、Cさんがその不動産の所有者になります。Bさんの方が先に購入していたとしてもです。
不動産の権利を明らかに
土地や建物は一見しただけでは誰が所有しているのかわかりません。
仮に誰かがそこに住んでいたとしても、その人が所有者とは限らないのです。もしかしたら、勝手に占拠して住んでいて、本当の所有者は別の人かも知れません。
登記の目的は、その不動産の権利関係がどうなっているのかを明らかにする事にあります。
登記によって不動産取引が安全に
もし、Bさんが直ぐに移転登記をしていれば、不動産の所有者はBさんになり、二重売買の被害を受ける事はありません。
後にAさんがCさんに二重売買をしようとしても、Cさんは登記記録を確認すれば、所有権がAさんに移転している事が分かるので、被害を受ける事はありません。
登記によって、第三者に対して権利を法的に証明できるので、不動産を買う側も売る側も安全で円滑な取引ができるようになるのです。
不動産登記が必要になるケース
不動産を売買した時はもちろん、登記内容に変更が生じた時など、概ね以下の様な場合に不動産登記が必要になります。
以下で、それぞれ詳しく見てみましょう。
家を新築した時
不動産登記法の第47条1項に、次のように記載されています。
不動産登記法 第47条1項
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
※衆議院HP「不動産登記法」より
「建物の表題登記」は義務です。家を新築した場合など、まだ登記されていない建物を取得した時には1ヶ月以内に「建物の表題登記」をしなければなりません。
もし怠ると10万円以下の過料が課せられる場合があります。
表題登記と一緒に、所有権を登記するための「所有権の保存登記」をするのが一般的ですが、保存登記は義務ではなく任意です。
未登記の土地を取得した時
不動産登記法の第36条に、次のように記載されています。
不動産登記法 第36条
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
※衆議院HP「不動産登記法」より
「新たに生じた土地」とは埋め立てや、海底隆起などにより、新たにできた土地ですが、そんな土地を登記する状況はまず無いでしょう。
「表題登記がない土地」とは未登記の土地のことで、もし、その様な土地を取得した時には1ヶ月以内に「建物の表題登記」をしなければなりません。
「土地の表示登記」も義務なので、もし怠ると10万円以下の過料が課せられる場合があります。
表題登記と一緒に、所有権を登記するための「所有権の保存登記」をするのが一般的ですが、保存登記は義務ではなく任意です。
登記されている不動産を取得した時
不動産登記法の第3条に、次のように記載されています。
不動産登記法 第3条
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。 一 所有権、 二 地上権、 三 永小作権、 四 地役権、 五 先取特権、 六 質権、 七 抵当権、 八 賃借権、 九 採石権
※衆議院HP「不動産登記法」より
すでに登記されている不動産を購入、あるいは相続した事で、所有者が他者から自分へ移った時には「所有権の移転登記」をします。
ただし、この移転登記は任意なので、しなくても罪にはなりませんが、後々、ややこしい事になるので、直ぐした方が良いでしょう。
建物を解体した時
不動産登記法の第57条に、次のように記載されています。
不動産登記法 第57条
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
※衆議院HP「不動産登記法」より
建替えのため、あるいは土地を更地にして売りに出すため、建物を解体した時には「建物の滅失登記」をします。
滅失登記は義務なので、1ヶ月以内に登記申請をしなければなりません。
もし怠ると10万円以下の過料が課せられる場合があります。
不動産の名義人が死亡した時
不動産の名義人が亡くなると、相続が発生して所有権が移ります。
その場合、不動産を相続した者が「所有権の移転登記」をします。
不動産登記法の62条で、次の様に定められています。
不動産登記法 第62条
登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。
※衆議院HP「不動産登記法」より
何を言っているのか、さっぱり分かりませんね。
第62条を要約すると
登記名義人または登記義務者、登記権利者が死亡した場合、相続人が代わって登記を申請できるという事です。
例えばこのようなケースが考えられます。
土地の名義人Aとその土地の購入希望者Bが売買契約を交わしたとします。
ところが、売買契約直後にAが死亡してしまった場合、Cという相続人がいれば、CとBで「所有権の移転登記」を申請できるということになります。
不動産に抵当権を設定した時
先に挙げた不動産登記法の第3条にある通り、住宅ローンやその他の借り入れのために、不動産を担保にした場合、「抵当権の設定登記」をします。
不動産登記法 第3条
登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。 一 所有権、 二 地上権、 三 永小作権、 四 地役権、 五 先取特権、 六 質権、 七 抵当権、 八 賃借権、 九 採石権
※衆議院HP「不動産登記法」より
金融機関の方で司法書士に依頼して「抵当権の設定登記」をするので、借りる側が特に何かをする必要はありません。
借金を全て完済した時
住宅ローンやその他の借り入れを全て返済した場合、「抵当権の抹消登記」をします。
抵当権を設定する時には金融機関の方で手続きを進めてくれましたが、「抵当権の抹消登記」は借金を返済した人がしなければなりません。
不動産登記法の第68条で、次の様に定められています。
不動産登記法 第68条
権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
※衆議院HP「不動産登記法」より
借金を全て返済した場合は、金融機関から証明書が送られてくるので、それを使って抹消登記を申請する事ができます。
住所や氏名の変更があった時
不動産登記法の64条1項で、次の様に定められています。
不動産登記法 第64条1項
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
※衆議院HP「不動産登記法」より
登記名義人が引越しなどで住所が変更した時や、結婚や養子縁組などで姓が変わった時には「住所・氏名の変更登記」をします。
このページの関連記事
![]() 登記事項証明書とは?
登記事項証明書とは?
‥‥登記記録とはどんなものか?
![]() 登記記録の表題部
登記記録の表題部
‥‥表題部には何が記載されているのか?
![]() 登記記録の権利部
登記記録の権利部
‥‥権利部には何が記載されているのか?
![]() 登記申請の手続き
登記申請の手続き
‥‥売主と買主が共同で登記申請をする
![]() 仮登記とは
仮登記とは
‥‥先にツバを付けておくというのが仮登記
★オススメの記事
